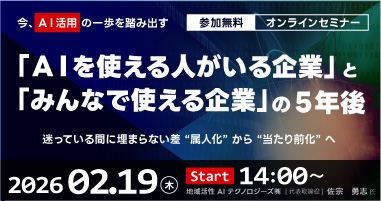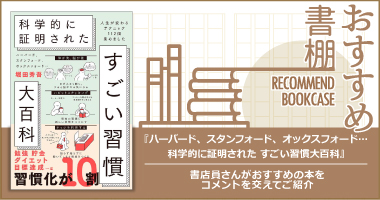『防災に対する日頃の備えが重要』/鈴木教授の特別講演
2025年06月21日(土)
SAGA建設技術フェア2025
その他
佐賀大学医学部看護学科の鈴木智惠子教授は、小児看護学が専門で、看護教育をはじめ、防災教育や災害時の医療的ケア児支援にも注力。特別講演では、被災地における避難所の実態を紹介した上で、防災に対する日頃の備えの重要性、使う人の声を聞いたハード整備などについて話した。
佐賀災害支援プラットホームやジャパンハートの事務局顧問など、多くの団体で要職を務めていた関係で、2018年以降に武雄市や大町町の内水氾濫、能登半島地震の避難所などを訪問。武雄市と大町町では、地域コーディネーターとして、避難所のアセスメントや訪問調査などを行った。
能登には発災後の3月に3泊4日で入り、門前中学校の保健室で寝袋生活をおくった。水が不足しており、トイレの水にも困る状況で、夜中にテントのファスナーを開ける音にも気を使う環境だった。発災から2カ月が経過し、疲弊する看護師をサポートした。
防災については「日頃から備えることを習慣化するのが大切。防災意識を持ち続ける方法として、定期的な避難訓練や防災マニュアルの確認などが有効」と説明した。
高齢者や子供、障害を持っている人などは、災害時に要配慮者となる。鈴木教授は「避難所や支援の現場では、専門知識だけでなく、寛容さ、温かさ、伝える工夫が求められる。出来たことを認め、出来ないことを責めない、分かり易く伝える。これは高齢者や子供、障害のある人など、支援を受ける全ての人にとって、安心できる大きな力になる」と述べた上で「配慮は特別なことではなく、ユニバーサルな優しさ。それが備える日常を作り、災害に強いまちの基盤になると考えている」と話した。
ハード整備に関しては「ハードを使う人の声を聞いてほしい。災害時に最も弱い立場にある人の命を守るためには、ハードの設計段階から当事者や支援者の実際の声を反映することが何よりも重要。例えば、車椅子の利用者が避難できるスロープについても、寝たきりの子供や重傷者を運ぶバギーが通れるのか、ということも考えてほしい」と話した。
さらに「医療的ケア児が安心して過ごせる福祉避難所の設備、機能だけでなく、現場で本当に役に立つかという視点での設計をお願いしたい」と語った。
このほか、特別講演では、三瀬や松梅地区の保育園での避難訓練、受援力(援助を受ける力)の大切さなどについても解説した。