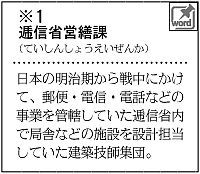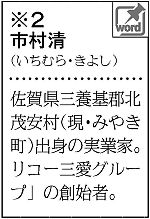県立博物館・市村記念体育館「半世紀を超えて」
2021年01月04日(月)
特集記事
その他
県立博物館の開館50周年にあわせて、2020年秋から県公文書館で県内の公共建築物についての資料展が開催されている。県内の主要公共施設の設計には、戦後日本の建築史に名を残す多くの建築家たちが関わってきた。その中でも、半世紀を超えて現存する2つの独創的な外観の施設について、設計者の思いや完成後の歩みとともに紹介してみたい。
■県立博物館■
昭和40年代に、国民の間で明治からの近代化の歩みを回顧し、評価しようという機運が高まった。それを受けて国は全国規模での明治維新百年記念行事・事業実施を計画する。佐賀県でも昭和42(1967)年に記念事業の実施が発表された。そのなかの一つが県立博物館の建設だ。総事業費は4億7000万円(当時)。設計は高橋一(たかはし・ていいち)と内田祥哉(うちだ・よしちか)。二人は明治期から日本の建築界をけん引してきた建築士集団・逓信省営繕課(※1)の出身。昭和37(1962)年に竣工した県立図書館での共作を皮切りに、高橋と内田は佐賀県の多くの公共建築物を手がけていく。
高橋と内田は、県立博物館に、佐賀県が今後大きく飛躍するための原点となるようにとの願いを込めて、建物が上部に向けて拡張していくデザインを考案した。当時の先端技術だった十字型プレキャストコンクリート梁を連結させていく「プレグリッドシステム」を採用し、大変な難工事の末に昭和45(1970)年に竣工した。
内田は「近代的博物館にふさわしい現代の先端技術をつかった工芸品」と自ら評した。また、その独特な外観について高橋は「佐賀の風土とはおよそかけ離れたものとして違和感を与えるが、それは狙いの一つ。この違和感がある限り、このまちに影響を与え続けるだろう」と語っている。建てて終わりではなく、その後の人々に与える影響をも見据えていることがうかがえる。
直線的な外観が目をひく県立博物館は、完成当時、上にいくにつれて広がっていくその姿に、空を目指して堂々と枝葉を伸ばす樟(くす・楠)を連想する人も多かったという。
竣工の翌年に日本建築学会賞作品賞を受賞した。
■市村記念体育館■
博物館とは対照的な優美な曲線と、それを縁取る突起が特徴的なのが市村記念体育館だ。昭和38(1963)年3月に竣工。当初は佐賀県体育館という名称だったが、平成4(1992)年に寄贈者の市村清(※2)にちなんで「市村記念体育館」と改称した。
折板状の外壁と楕円形の吊屋根で構成されていて、県内唯一の吊屋根工法の公共建築物だ。ユニークなのは東西両端からスロープ状に突き出た梁で、これは屋根に降った雨水を落とす樋の役目をはたしていて、その先には大きな円形の水溜めがある。
設計を手がけたのは坂倉準三(さかくら・じゅんぞう)。世界的名建築家ル・コルビュジエを師と仰ぎ、昭和12(1937)年のパリ万国博覧会で日本館の設計を手がけ、高い評価を受けた。昭和39(1964)年からは日本建築家協会の会長を務めた。
平成23(2011)年の東日本大震災以降、建築基準法などが改正されて、人々の防災意識も高まった。そうした時流を受け、市村記念体育館は老朽化と競技用フロアの狭さなどを理由に県が策定した「佐賀県総合運動場等整備基本計画」でスポーツ施設としての使用を終了することになった。
しかし平成27(2015)年に、隣接した県立図書館、大楠などの木々や広場と合わせて佐賀市景観賞を受賞。さらに平成30(2018)年に開催された「肥前さが幕末維新博覧会」ではメインパビリオン「幕末維新記念館」として、翌年の全国高等学校総合文化祭・さが総文では芸術・工芸部門の会場として多くの来場者を迎えた。県は市村記念体育館の今後について、有識者による委員会などを設けて、文化的、歴史的背景を生かした利活用の道を検討していくとしている。
●公共の空間の核として
対照的な姿の県立博物館と市村記念体育館だが、大きな共通点がある。どちらも周囲に広々とした空間があり、人々が集ってくるということだ。散歩を楽しむ人や、ベンチでのんびりと過ごす人が絶えない。近隣の学校から画板を抱えてやってくる児童生徒たちの姿もよく目にする。
たんなる博物館、体育館としてだけではなく、そこにあることで、誰もが見上げてくつろげる憩いの場としてしまうその存在感。まさに公共の空間の核、人々の心の拠り所としてふさわしい。
◆ 資料展11日まで
佐賀県公文書館(県庁南館)は、11日まで佐賀の公共建築にスポットを当てた所蔵資料展を開催している。入場は無料。県内の主要公共施設の設計図面(複製)、石膏模型、当時の専門誌、県公報誌(複製)など23点を展示。建築家たちが設計に込めた「さが」の発展への思いを紹介している。