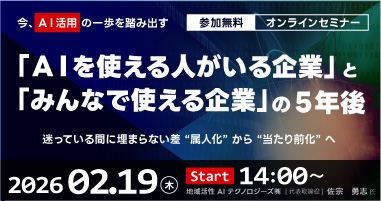水ものがたり館北側 /兵庫竹林で竹切り活動 /佐賀県農業土木振興会
2019年12月14日(土)
地域貢献
地域貢献
佐賀県の農業土木職員OBでつくる「佐賀県農業土木振興会」(原憲義会長、会員19人)は6日、佐賀市のさが水ものがたり館北側にある石井樋公園内の兵庫竹林で牡蠣礁復活のための竹切り活動を行った。荒牧軍治館長(佐賀大学名誉教授)から戦国時代から江戸時代初期に活躍し「水の神様」と呼ばれた土木技術の達人、成富兵庫茂安が築造した石井樋の利水、治水事業の役割と功績について話してもらい、石井樋群の現地説明を受けた後、竹切り活動に着手した。
同会は建設コンサルタントの技術向上、情報交換、事業の発展などに寄与することを目的として2011年5月に発足。現在は、県の農業土木OBで県内の建設コンサルタント会社に勤務する19人で組織している。本年度の年間事業計画に沿って実施したもので、活動には会員11人が参加した。
石井樋の説明では荒牧館長が、12月4日にアフガニスタン東部で知人の中村哲医師(ペシャワール現地代表)が殺害されたことを取り上げ、「中村医師は医療活動だけでなく、現地の人々の幸福のために食糧生産、農地の回復が必要と考え、井戸掘削や取水施設、水路建設など、農業用水のかんがい事業に自ら率先して取り組まれていた。福岡出身であり、取水施設や水路建設については成富兵庫の水利技術を学ばれ、佐賀の技術がアフガニスタンで活用された」などと説明。会員は深く感銘を受けた。
その後、さが水ものがたり館元職員の服部二朗氏から、石井樋群(大井手堰、かめ石、二の井手堰、天狗の鼻、象の鼻、石井樋など)について、①洪水を防ぐ②川の勢いをゆるめる③水の量を調節する―など、石井樋の働きに関する説明を受け、会員は佐賀平野の恵みを知るとともに、400年前にタイムスリップした気分を味わった。
現地説明を受けた後、昨年同様に有明海牡蠣礁(かきしょう)復活に活かすため、同館北側の兵庫竹林に移動して竹切り作業に着手。参加者は、丸さ2~3㌢の竹を切り出すグループと、長さ約120㌢に切りそろえるグループに分かれ、2時間の作業で912本を効率よく仕上げた。
「森川海人っプロジェクト」では、来夏の牡蠣礁づくりに向け、約7000本の竹を用意する予定。