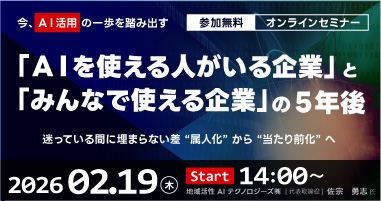災害に備え研修会 /災害復旧申請、技術の継承 /武雄市農村災害ボランティア
2019年07月09日(火)
地域貢献
地域貢献
武雄市や佐賀県農林事務所の退職者も交えた「武雄市農村災害ボランティア」(山口亀男会長、33人)は3日、昨年の西日本豪雨を振り返る研修会を行った。冒頭、新しく会長に就任した県OBの山口氏が「技術者の世代交代で災害復旧事業の申請や復旧工法など技術の継承が難しくなり、経験者の体験や意見を聞く機会が重要になっている」とあいさつした。
研修会では2018年度災害の概要について市が、農地、農業用施設、林道災害など66カ所で約1億円の査定額となったことを報告。ため池災害の復旧事例として若木町のため池の事例を紹介し、「パイピングにより余水吐きの下部まで空洞が続いており、堤体部の前刃金土による埋め戻しと併せて空洞にはモルタルを充填した」と解説した。会員からは「空洞の充填には十分に圧力をかけて注入しないと末端まで充填しにくい」などの意見が出た。
次に杵藤農林事務所から県全体の被害報告があり、併せて山内町で発生した棚田地帯における農地の亀裂について説明があった。担当者は「災害復旧事業(農地保全)と地すべり対策事業のいずれかで対策工事を検討したが、広範囲にわたることなどから地すべり対策事業として申請することになった」と話した。これに対し、会員からは「地すべり防止区域を設定した場合、開発行為などに様々な制限を受けることになるが、地元の了解はどうだったのか」などの質問が出た。
最後に県OBの大宅公一郎氏は、西日本豪雨でため池の破堤が多数報告されていることを踏まえ、10年7月に川良区の内の子ため池沿いの県道法面が崩落し、県道を超え、もう一歩で土砂が余水吐きまで埋めそうになった当時の写真や、武内町の新堤ため池が早朝決壊し、危うく県道まで土砂が覆い被さるところだった当時の緊迫した写真を提示し、「武雄市ではため池ハザードマップが20カ所作成されているので、近隣住民はもとよりホームページなどで広く市民に知らせるべき」と要望した。
同ボランティアは、全国7カ所のモデル地区として04年8月に設置され、今年で16年目を迎えた。武雄市農林課農村整備係を中心に、県杵藤農林事務所、土地改良事業団体連合会、および武雄市や県農林事務所の退職者などで組織され、今回の活動には21人が参加した。
今回の研修では現地視察を予定していたが、梅雨前線が北上中で大雨の予報もあり、室内での研修に切り替えた。